はじめての盆栽
盆栽に関する知識・盆栽の作り方・育て方を共に学びながらはじめての盆栽に挑戦しましょう!!
目次
盆栽の基本
盆栽とは?
自然界にある植物を鉢に植えこみ、針金などで強制的に幹や枝を曲げて自然界にある樹形の姿に仕立て上げていきます。
つまり、鉢に植物を植えこみ自然界にある姿(樹形)を小さくまとめて表現しその美を眺めて楽しみます。
ミニ盆栽は、さらに小さく作り上げていきます。
そして、樹形が仕上がってくるに従い鉢も変えていき樹形と鉢の組み合わせで美しさを表現します。
何百年、何十年と世代を通して育てられた盆栽は見事なものです。
自分で作り上げた盆栽を、玄関や部屋に飾った時の自己満足の境地は最高に間違いありません!
盆栽の種類
木もの
- 松柏類
- 雑木類
- 花もの
- 実もの
各盆栽の特徴
松柏類の特徴
松柏で真っ先に浮かぶのが松を思い出す人が多いのではないでしょうか。
クロマツ、アカマツ、ゴヨウマツ、シンパク、スギ、ヒノキ、イチイなどがあります。
松柏類は、剛健で長生きするものが多いことから、生命力の象徴と喜ばれています。
雑木類の特徴
落葉樹は、春の芽だし、初夏の新緑、夏の緑葉、秋の紅葉と黄葉と四季折々に変化しますので一年を通して楽しめる盆栽です。
さらに、様々な樹形に作りやすく丈夫で育てやすい樹種が多いので初心者の一鉢にお勧めです。
モミジ、カエデ、ケヤキ、ブナ、ヒメシャラなどがあります。
枝先の細やかさや葉の色や形、幹肌などを鑑賞できます。
花ものの特徴
サクラ、サツキ、ウメ、ボケ、ツバキ、チョジュバイ、ツツジなどがあります。
花もの(盆栽)は、松柏類や雑木類と違って花と樹形の両方を楽しめます。
四季に合わせて咲く花を揃えれば年を通して楽しめます。
その中でも、サツキは成長も早く初心者向けにうってこいの一品です。
実ものの特徴
実は、人が楽しむだけでなくその実を食べに鳥が訪れることもあります。
愛らしい小鳥を眺めているとホット一息できます。
ヒメリンゴ、クチナシ、ピラカンサ、マユミ、カリン、マンリョウなどがあります。
盆栽の樹形
直幹
自然界で例えると丘の上で風も強すぎず、日当たりの良い理想的な環境で育った樹木の樹形を目指します。
幹は、上に行くほど細くなり枝の間隔も徐々に狭くなり、枝と根が四方八方に伸びているのが理想の形です。
クロマツ、スギ、ヒノキ、トショウなどが直幹に向いています。
双幹
強くて高い方を主幹、低くて弱い方を副幹と呼んでいます。
双幹に向く植物は
松柏類では、ゴヨウマツ、アカマツ、エゾマツ
雑木類では、モミジ、カエデ類
花もの・実ものでは、サクラ、ウメモドキ
模様木
幹に曲がりを持ちながら立つ植物の姿を現し、直幹に比べ荘厳でどっしりした印象。
曲がり具合に大小はありますが、直幹性の植物を除いて自然環境の中で生えている木のほとんどが最終的にはこのような樹形になります。
模様木は、曲線美を楽しみます。
ほとんどの樹種で作ることができます。
スギ・ヒノキ・ケヤキなどの幹が直線的な樹種は向きません。
斜幹
自然界では、強風に煽られて幹が斜めに傾き、今にも倒れそうになっている樹木を想像してみましょう。
今にも倒れそうな姿を出しながら、枝や根張りなどでバランスを取り不安定さを出さないようにするのがおさえどころ。
直立性の杉や檜の他、松柏類や花物、実物などほとんどの樹種は斜幹にできます。
懸崖
幹や枝を鉢底より下げたものを懸崖、鉢縁より下がる程度の物を半懸崖と呼びます。
懸崖に向いている植物は
松柏類では、ゴヨウマツ、クロマツ、トショウ、シンパクなど
雑木類では、ツタ
花ものでは、サツキ、カイドウ、ウメ、ボケなど
実物では、柑橘類など
寄せ植え
つまり、同じ樹種を複数植えこんで森や林のように作ります。
三本以上の奇数が良いとされていて、上限はありません。
寄せ植えに向いている植物は
松柏類では、ゴヨウマツ、トショウ、エゾマツ、過ぎ、ヒノキ
雑木類では、モミジ、ブナ、ケヤキ、トウカエデなど
花ものでは、サクラ、チョウジュバイ
実物では、ピラカンサ、ウメモドキなど
石付き
石にケト土で植物を植えこみ荒々しい岩場に生えている姿にみせるようにします。
松柏類では、クロマツ、エゾマツ、ゴヨウマツなど
雑木類では、モミジ、カエデ
花ものでは、チョウジュバイ、ボケ
実物では、サンザシなど
盆栽の種類
盆栽は、大別して木もの・草ものとなります。
さらに、木ものを
- 松柏類
- 雑木類
- 花もの
- 実もの
と小分けされています。
盆栽と言えば、木ものが目に浮かびます。
草ものは、初心者には、難しいのでは?
ここでは、木ものの方を取り上げて紹介します。
これから、木ものの各種類の特徴を紹介します。
松柏類の特徴
松柏で真っ先に浮かぶのが松を思い出す人が多いのではないでしょうか。
クロマツ、アカマツ、ゴヨウマツ、シンパク、スギ、ヒノキ、イチイなどがあります。
松柏類は、剛健で長生きするものが多いことから、生命力の象徴と喜ばれています。
雑木類の特徴
落葉樹は、春の芽だし、初夏の新緑、夏の緑葉、秋の紅葉と黄葉と四季折々に変化しますので一年を通して楽しめる盆栽です。
さらに、様々な樹形に作りやすく丈夫で育てやすい樹種が多いので初心者の一鉢にお勧めです。
モミジ、カエデ、ケヤキ、ブナ、ヒメシャラなどがあります。
枝先の細やかさや葉の色や形、幹肌などを鑑賞できます。
花ものの特徴
サクラ、サツキ、ウメ、ボケ、ツバキ、チョジュバイ、ツツジなどがあります。
花もの(盆栽)は、松柏類や雑木類と違って花と樹形の両方を楽しめます。
四季に合わせて咲く花を揃えれば年を通して楽しめます。
その中でも、サツキは成長も早く初心者向けにうってこいの一品です。
実ものの特徴
実は、人が楽しむだけでなくその実を食べに鳥が訪れることもあります。
愛らしい小鳥を眺めているとホット一息できます。
ヒメリンゴ、クチナシ、ピラカンサ、マユミ、カリン、マンリョウなどがあります。
盆栽用樹木
盆栽に初めて挑戦するとき、盆栽の素材となる樹木がなくてははじまりません。
どんな種類の樹木が盆栽に向くか把握しておきましょう。
盆栽用樹木の種類
- 松柏類
- 雑木類
- 花もの
- 実もの
各種とも多品種ありますが人気者をピックアップして紹介します。
松柏類
松柏類で盆栽として多くの人に愛されてきたのが真柏と五葉松といっても過言ではないでしょう。
松柏類は、実生苗・鉢植えの物など数多くあり入手しやすい素材です。
五葉松
幹や枝の柔らかな線が特徴で、剪定や針金がしやすくいろんな樹形で楽しめます。
苗も入手しやすく選ぶときは、根張り・葉性の良い物を選ぶ。
真柏
幹が自然に捻じれシャリとしても楽しめます。
丈夫で育てやすく鉢植え・ポット苗も入手しやすい素材です。
初心者向けにお勧めの樹木です。
雑木類
盆栽では、落葉樹を雑木類に分類します。
落葉樹は、春の芽だし、初夏の新緑、夏の緑葉、秋の紅葉と黄葉と四季折々に変化しますので一年を通して楽しめる盆栽です。
さらに、様々な樹形に作りやすく丈夫で育てやすい樹種が多いので初心者の一鉢にお勧めです。
もみじ、カエデ、ケヤキ、ブナ、ヒメシャラなどがあります。
枝先の細やかさや葉の色や形、幹肌などを鑑賞できます。
もみじ
紅葉を楽しむ雑木類盆栽の代表格。
春の芽出しや初夏の新緑も美しく、丈夫で育てやすいので初心者にも向いています。
古木の白い幹肌に走る縦縞模様も見事です。
ブナ
秋には、緑から黄色・オレンジ色・金茶色と葉の色が変わり木葉の移り変わりが楽しめます。
冬の葉が茶色となり枯れ葉となったさまは、まるで深山の冬枯れの景色を思い出させてくれます。
寄せ植えにしてブナ林の風景を楽しむのもおすすめです。
花もの
盆栽では、花を鑑賞するものを花もの(盆栽)に分類します。
梅、長寿梅、桜、皐月、ボケ、椿、ツツジなどがあります。
花もの(盆栽)は、松柏類や雑木類と違って花と樹形の両方を楽しめます。
四季に合わせて咲く花を揃えれば年を通して楽しめます。
その中でも、梅・長寿梅は初心者向けにうってこいです。
梅
花の少ない寒中に咲き、春の近づく感じをさせてくれます。
かすかな香りも楽しめお部屋の一角に飾れば一段とお部屋を引き立ててくれます。
室内で鑑賞するときは、つぼみの落下を防ぐため、キリフキで水をかけると良いそうです。
長寿梅
ボケの一種で、秋から春にかけて繰り返し花が咲きます。
花色は、赤と白が主です。
ボケに比べて細かい枝や葉がでるのが特徴です。
実もの
盆栽では、実を鑑賞して楽しむ盆栽を実もの盆栽に分類します。
実は、人が楽しむだけでなくその実を食べに鳥が訪れることもあります。
愛らしい小鳥を眺めているとホット一息できます。
ピラカンサ、マンリョウ、ヒメリンゴ、クチナシ、マユミ、カリンなどがあります。
ピラカンサ
初夏に、小さい白い花が咲き秋になると花の数だけの赤い実が鈴なりに実をつけます。
枝にトゲがあるのが特徴です。
マンリョウ
お正月に縁起物として親しまれています。
年末になると切り花としても登場します。
常緑の葉と真っ赤な実のコントラストが華やかです。
但し、マンリョウは、雄木と雌木がないと実をつけてくれないそうです。
盆栽道具
いざ、盆栽を始めようと思っても物がなくてははじまりません。
樹木・植えこむ土・植えこむ鉢
そして、盆栽を仕立てていく道具などが必要となります。
これから、紹介する盆栽道具は代用できるものもありますができたらすこしずつ専用の道具を揃えていくのも楽しみの一つになります。
まず、使用頻度の高い物から用意して必要に応じて徐々に揃えていくのも良いと思います。
盆栽道具の種類と用途
回転台
盆栽を仕立てていく際、正面・裏面・右面・左面とあらゆる方向から樹形の姿を見ながら作業をすることになります。
そんな時、役立つのが回転台です。
回転台を使うと作業がはかどるうえ超便利です。
本格的に盆栽を始めようという方はぜひ揃えておきたい道具です。
昇降式回転台
回転台を好みの高さに調節できるようになっています。
盆栽の丈に合わせて調節したり、自分の座高に合わせて高さを調整でき仕立て作業が楽にできます。
普通の回転台
用途は、昇降式回転台とおなじですが高さ調整ができません。
作業する場所が広くない場合などに使うようにになります。
ちなみに、自分はこちらを使用しています。
必要に応じて別途、用意した台の上に卓上式回転台を載せて高さを調整しています。
ジョウロ
盆栽に水をあげる道具です。
一般のプラスチックのジョウロだと目が粗く水の勢いが強すぎて、鉢上の用土やコケを流してしまう恐れがあります。
盆栽用ノズル
盆栽の数が多くなったらこちらが便利です。
水のでる目が細かいのを選びます。
手元にコック付きものや先端が交換できるものもあります。
盆栽用 ジョウロ
園芸用のプラスチックのジョウロに比べて目が細かくできています。
目が細かくなっており水が優しくでるので用土を流してしまうことを防げます。
盆栽の数が少ない時はこちらのほうが良いでしょう。
剪定バサミ
太い枝を切るときに使います。
枝切りバサミでは切れないような太い枝を切る時に使います。
右利き用と左利き用がありますので自分の利き手に合った方を選びましょう。
枝切バサミ
盆栽で最も基本の剪定するときに使うハサミです。
小枝を剪定するときや、芽摘み、葉刈などの時に使います。
コブ切りバサミ
大きな枝の切口を整えたり、幹にできたコブを切り取るとき使います。
切り出し小刀
さし木・つぎ木・とり木をする時に使います。
盆栽用針金切りバサミ
針金をかけて盆栽の樹形を作りますその時、針金の切断に使います。
根切りバサミ
太い根を切るとき使うハサミです。
盆栽用 土入れ
用土を鉢に入れる時に使います。
土フルイ
用土の微塵を取り除くときにこのフルイにかけて取り除きます。
用土の粒の大きさを調整するときも使います。
用土
赤玉土・鹿沼土・桐生砂・日向砂が主に使われています。
針金
樹形を作るとき・株を止める根止め・鉢底ネットを鉢底穴に固定する時に使います。
枝の太さに応じて径を変えていくため1.2mm/1.5mm/2.5mm の太さの針金を用意しておきましょう。
針金の材質は、アルミニウムと銅。
枝の太さに応じて使い分けます。
枝が細く柔らかい枝にはアルミニウムの方を使います。
硬い枝や幹には銅線を使います。
鉢底ネット
鉢底に敷いて、土の流出防止や防虫に使います。

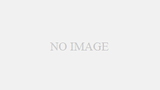
コメント